
熊本県荒尾市に拠点を構える「荒尾フットボールクラブ」(以下荒尾FC)は、2003年の創立から今年で23年目を迎えました。
地域の子どもたちのためのクラブとして歩みを始めた同クラブは、ジュニアユースやNPO法人化などを経て、今や大きな地域密着型クラブに成長しています。
代表の山代 進さんに、クラブ設立の経緯や子どもたちとの関わり方、そして“継続”に込めた想いについてお話を伺いました。
お話を聞いた人
大学3年生時に地元の中学校サッカー部の外部コーチからスタートし、2003年ジュニアクラブとなる荒尾JFCを設立。
2010年にはジュニアユースとなる荒尾FCを設立し、チームの代表としてはもちろん、地元の体育協会理事として小中学校の社会体育移行支援や、熊本県クラブユースサッカー連盟副委員長、ウェルフェアオフィサーや4種トレセンスタッフなど様々なかたちで活動をされておられます。
地域に支えられて歩む
ーーー創立が2003年ということですが、この22年間はどのような時間でしたか?
荒尾FC 代表 山代 進(以下、山代)
正直なところ、当初はこんなに長く続けるつもりなんてなかったんですよ。
チーム名に“荒尾”という地域名が入っているのですが、それが最大のメッセージです。
「この地域の子どもたちのためのクラブでありたい」という想いだけはずっと変わらずに持ち続けてきました。
ジュニアユースを立ち上げたのが2010年、そしてNPO法人化したのが2019年です。
その想いに共感してくれたスタッフ、保護者の方々や地域の皆さんに支えられて、今23年目を迎えられているという実感があります。
ーーー選手は基本的に荒尾市内の子どもたちが中心ですか?
山代
もともとジュニア(小学生)を立ち上げた当初は、「荒尾市内の小学生」という入会条件を設けていました。
今ではかなり珍しいケースだったと思いますが、それは「無理なく通える子どもたちに来てほしい」という想いからでした。
2010年にジュニアユースを立ち上げてクラブ連盟への加盟する際に「地域を限定してはならない」というご指摘をいただき、その時に条件を撤廃しました。
現在は、福岡県の大牟田市や熊本県内の玉名郡市などからも、車で30分ほどかけて通ってくれている子もいます。
しかし、あまりに遠すぎる場合は、無理して欲しくないとも考えています。
以前、県外から片道1時間20分もかけて体験練習に来てくれた子がいました。能力的にはとても楽しみな選手でしたが、正直入会をあまりお勧めはしませんでした。
トレーニング後に帰って、お風呂に入って、ご飯を食べて、宿題をして…という日常を想像したときに、中学生の生活として現実的ではないと思ったからです。
サッカーだけでなく、学校や家庭での時間も含めて「生活」がある。
だからこそ「通える範囲で、無理のない選択をすること」も、長く続けていくうえでは大事な視点です。
ーーー高校での進路を選ぶときも、無理のない選択を基準にしていますか?
山代
ありがたいことに、熊本県には大津高校さんを筆頭に強豪校も沢山ありますし、Jクラブのロアッソ熊本ユースなど、サッカーに打ち込める選択肢は十分に整っています。
ですから、選手や保護者の志望を尊重したうえでが前提ですが、まずは県内で“生活と競技の両立が可能な道”を推奨しています。
どんな環境でも結局は“その子自身がどう取り組むか”だと思っています。
環境のせいにしてしまうと、いずれ社会に出てからもなかなか自分の力を発揮しきれなくなってしまう。
「この高校だから活躍できなかった」「あのチームだったら…」という外への矢印ではなく、どんな環境でも“自分がどう動くか”を考えられる選手が、最終的に成長していくんじゃないかと感じています。
「ちゃんと見ているよ」と伝え続ける
ーーー地域に根ざしながら、今回は九州大会(※九州クラブユースU-15選手権)にも出場されましたね。
山代
ありがたいことに、今回で5回目の九州大会出場となりました。
ちょうど同じタイミングで、小学6年生たちも熊日学童五輪に出場していて、県ベスト8に入ることができました。もちろん、そういった成果は素直に嬉しいです。
ただ、こういった結果が嬉しいというのは間違いないのですが、僕自身は常々そこだけを優先し過ぎないように気を付けています。
活躍の裏で県大会、九州大会に出場出来なかった子たち、対象外の学年の子たちにもしっかり活動の場を用意し続ける事、すべての子どもたちに目を向けながら上位を目指していくことが、大切だと思っています。
ーーー子どもたちの“目に見えづらい成長”を、どのように伝えているのでしょうか?
山代
「リフティングやドリブルの出来る種類が増えた」とか、「苦手だった左足で蹴ろうとチャレンジした」とか、そういった小さな変化をちゃんと見つけて、言葉にして伝えることが大事だと思っています。試合での得点や勝敗はもちろん大事ですが、それだけでは見えてこない成長がたくさんあるんです。
たとえば、今できるようになったことに本人が気づいていない場合もありますよね。だからこそ僕たち指導者が気づいて、「今のプレー、すごくよかったよ」「前はできなかったのにできるようになってるね」と伝える。それが子どもたちの自信につながるんです。
「得点王」や「アシスト王」といったわかりやすい評価もありますが、そこに届かない子の方が圧倒的に多いと思うんですよね。そうした子どもたちの努力や変化を見逃さず、「ちゃんと見てるよ」と伝え続けることが大事だと思っています。
最近は、「褒める」っていうことがすごく大事だっていう認識が広まってきていて、自分もそれは本当に大切なことだと思ってるんです。
でも一方で、子どもがちゃんと取り組めていないことに対して、それをきちんと伝えることも大事だと感じています。
たとえば、「さっきのトレーニングの中で、君こういうこと言ってたよね。仲間に対してああいう発言があったけど、あれってどう思うかな?」って問いかけたときに、子ども自身が「あれはまずかったな」って気づく。
そしたら、「じゃあ次どうする?」って話につなげていく。そういうやりとりって、すごく大切だなって思うんです。
叱るというよりも、良い面も悪い面もちゃんと伝えてあげることが、子どもの成長にはすごく必要なんじゃないかなと感じています。
対話を大切に
山代
今、うちのクラブは小学生が約100名、中学生が約70名。
人数が多いので、一人ひとりと丁寧に話す時間は限られていますが、練習の合間や試合のタイミングで、保護者の方ともできるだけ対話するようにしています。「最近うちの子、調子悪いんじゃないか」と言われても、「いや、実はこんな成長がありましたよ」と伝えられるようにしています。
僕は今年度、主に小学校低学年のトレーニングを担当しているんですが、練習が終わった後には必ず、全学年を1列に並ばせて、その日に起こった“良かったこと”“課題だったこと”をみんなに向けて伝える時間をつくっています。
これは子どもたちだけでなく、送り迎えに来ている保護者の方にも聞こえるように、しっかり声に出して話しています。
ーーーコロナ以降、対話が苦手な子が増えているとも言われますが、荒尾FCに入ったばかりの選手と卒団する選手では、発信力などに変化はありますか?
山代
そうですね、やっぱり「ちゃんと喋ってくれる大人がそばにいるかどうか」は大事だろうなと思っています。
もちろん、子どもたちの成長のスピードには個人差がありますし、性格もいろいろです。だから全員がうちに入ったからといって、みんながみんなコミュニケーション力が高くなるかって言うと、そうではないと思います。
でも、考え方の芯の部分はしっかり持って卒団していってほしい、というのが僕の思いです。逆に、対話が苦手な子がいれば、そういう子にはまた別の良さがあると思うんです。
みんなが金太郎飴みたいに同じじゃないし、プレーも性格も違う。例えば、人前で話すのが苦手でも、陰でコツコツ努力する子や、誰も見てないところで片付けや準備を頑張ってくれる子がいます。
そういう子の良さをちゃんとみんなに見えるように伝えていく。それも大事なことだと思っています。
なので、活動の最後に振り返りの話をする際も子どもたちにだけ伝えるのではなくて、お迎えに来ている保護者の方々にも聞こえるように、良いことも悪いことも全部オープンに伝えます。
そうすることで、透明感というか、「あ、このクラブはちゃんと子どもたちに目を向けてくれているんだな」っていう安心感にもつながると思っています。
ーーー保護者との信頼関係も、育成には欠かせない要素なんですね。
山代
そうですね。お迎えがギリギリになった方でも、「今日はこんなことがあったんだ」とその場でわかるようにしているつもりです。
いい話ばかりではなく、時には耳が痛いようなこともあるんじゃないかと思います。
それも含めて、子どもたちの“リアルな姿”を保護者の方々と共有したいと思っています。
家庭で過ごす時間のほうがクラブよりも圧倒的に長い。
だからこそ、クラブでの出来事がご家庭での会話のきっかけになることを願っています。
「今日こうだったんだね」「じゃあ次はこうしてみようか」っていう会話があるだけで、子どもたちも次の練習に前向きな気持ちで戻ってこられる。
それが一番理想的な成長のサイクルだと思っています。
ーーー対話が大切だなと実感するようになったのはなぜでしょうか?
山代
やっぱりサッカーって、コミュニケーションのスポーツだと思うんですよね。
それで、保護者の方々にも「応援マナーのサポーター8ヶ条」をクラブの方針としてお伝えしています。
もちろん、今はネットで調べればいろんな情報が出てきますけど、やっぱり本質的な部分っていうのは、実際に話をしないと伝わりにくいと思っています。
それに、まず自分自身のことを知ってもらう事が、クラブを理解してもらうには一番の近道かなと思ってるんです。
僕自身、正直サッカー選手としては全然大したことなかったですし、プロなんて本当にまったく夢のまた夢でした。
だからこそ、元Jリーガーとか元代表選手の方々が夢を語ることには、本当に意味があると思ってます。
でも僕にはそれができない。なぜなら、そういう経験をしてきたわけじゃないからです。
逆に、そんな自分でも、この地域でサッカーを伝える立場にいられるということ。これは事実としてちゃんと伝えたいと思っています。
今、たとえば試合でスタメンに入れない子がいたとしても、「でもサッカーが楽しいって思えているなら、それでいいじゃん」って。関わり方はいろいろあるってことを、ちゃんと伝えてあげたい。
僕自身も、これまでたくさんの人との関わりの中で、声をかけてもらったり支えてもらったから、今の自分があると思っていて。
だから今度は、もらう側から与える側になることが、自分の使命なんじゃないかなと、そう感じています。
「このクラブを衰退させない」
ーーー指導者として「やっていてよかった」と感じるのは、どんなときですか?
山代
先週あった熊日学童五輪という県大会のことです。うちには現在6年生が23名いて、2チームに分かれて出場したんですが、1チームは惜しくも敗退して、もう1チームが勝ち上がったんですね。
その後も勝ち上がり、翌々週のラウンド16の試合には「時間がある子は応援に来てくれると嬉しい」と声をかけたら、本当にたくさんの子どもたちが、1時間半以上かかる会場まで応援に来てくれたんです。自分が試合に出るわけでもないのに。
そして保護者の方々も一緒に来てくれて、後から聞いた話では、低学年の保護者の方まで来てくださっていたそうで…もう本当にチーム愛を感じれた瞬間で嬉しかったですね。
また、地元高校のグラウンドを芝生化する”JFAグリーンプロジェクト”にもクラブとして協力して取り組んでいるんですが、その作業の日もすごかったんです。
「お手伝いいただける方はぜひ」とお願いしたところ、小雨の降るあいにくの天候だったにもかかわらず、本当にたくさんの保護者の方々やOBの保護者まで子どもたちの未来のためにと集まってくださいました。
高校の先生たちもびっくりされていて、生徒たちと合わせて200人くらいになってしまって(笑)。結果的に、予定していた時間よりもずっと早く作業が終わったんです。
そういう瞬間に立ち会うたびに、「地域がつながるって、こういうことなんだな」と感じますね。
今回、2年ぶりに九州大会に出場させていただいたときも、OBの子たちや、かつて関わってくださった方々から「見てます」「頑張ってください」というメッセージがたくさん届きました。その場にいなくても、つながっていることが実感できる。
そういう瞬間こそが、指導者としての一番の喜びです。
だからこそ、その“責任”ってすごく大きいと感じていて。
「山代、まだ元気にやってるな」っていうのを見せ続けることが自分の大事な役割だと思っています。
正直、試合の勝ち負けに関しては、僕自身よりも、日々子どもたちと向き合ってくれているコーチ陣の頑張りの賜物であって、いわば“ボーナス”のようなものだと捉えています。
僕が担うべきは、このクラブを衰退させないこと。
地域とのつながりを大切にしながら、長く継続できる土台を支えること。
それが、今の自分にとっての最大の使命です。
現在では、新入生募集の広告も毎年新U-13クラスをアナウンスする程度で他は一切やっていません。それでも入ってきてくれるのは、本当にありがたいことだと思っていますが、結局はクラブをきちんと理解して、「ここでやりたい」と思って来てくれる子が一番伸びるし楽しめると思うんですよね。
サッカーを「楽しむ」場所として
ーーー荒尾FCを卒業後、選手たちにはどのような進路がありますか?
山代
進路は本当にさまざまです。
高校サッカーの強豪校を目指す子もいれば、地元の高校を選ぶ子もいます。
僕自身、そしてクラブとして大切にしているのは、まず「子ども自身の意向を尊重する」ことです。
高いレベルにチャレンジしたいという意志があれば、その気持ちにしっかりと寄り添い、できる限りのサポートをします。
一方で、こちらから進路を誘導したり、無理に進めたりすることはありません。
ーーー強豪校に進まず、別の道を選んだ子もいるのでしょうか?
山代
はい、実際にスタメンで活躍していた選手が進学校を選んだケースもありました。
指導者としては「もっとサッカーで上を目指せるのに」と思う気持ちもありましたが、彼が選んだ道を応援したいと素直に思いました。
サッカーは判断のスポーツです。
だからこそ、人生の進路も自分で判断して、最後は自分の意思で進んでいくことが大切だと思っています。
ーーー小学生の中には体格に不安があるお子さんや、技術的に「うちの子はサッカーに向いてないかも」と悩む保護者の方も多いと思います。そういった子でも、荒尾FCで頑張れますか?
山代
実はそういうご相談、本当に多いんです。でも、子どもがどう成長するかなんて、正直誰にも分からないと思っていて。まだ小学生なのに今現在、背が低いとか、足が遅いとか、そんなことだけで「向いてない」って決めてしまうのはもったいないですよね。
僕自身、身長も低くて、足も特別速かったわけじゃありません。
「小さい子ばっかり集めてません?」なんて冗談を言われることもあります(笑)。
でも、だからこそ、体格に悩む子や保護者の気持ちはよく分かるんです。
個人対個人では勝てなくても、それぞれが役割を果たすことでチームとして勝利する。結局は個人競技ではなくチームスポーツですので、出来ることを増やしつつ、役割を与えてあげることが出来れば体格や技術の差を埋めることは可能だと思っています。
また、僕がいつも伝えるのは、「じゃあ、何が成功なんだろう?」ということ。
サッカーって、まずは“楽しい”が出発点であるべきです。
試合に出られなかったとしても、一生懸命に練習して、仲間と笑い合って、充実した時間を過ごせたなら、それはもう立派な「成功」です。
実際、今コーチとして戻ってきてくれているOBの中には、当時スタメンじゃなかった子もいます。
彼らは「サッカーって楽しい」という気持ちをずっと持ち続けてくれていた。
そういう姿を見ると、うちのクラブが大切にしてきたことは間違ってなかったなと、実感します。
ーーー最後に、これから入団を考える小学生や保護者の皆さんに、メッセージをお願いします。
山代
サッカーは勝敗のあるスポーツですから、“勝ちたい”という気持ちは大切です。
でも、僕がいつも子どもたちに伝えているのは、“監督が勝ちたいんじゃなくて、自分たちが勝ちたいと思えることが大事だよ”ということ。
冗談交じりに「コーチは正直どっちでもいいんだから」って言うこともあるんです(笑)。それくらい、“自分でやりたい”という気持ちが一番大事なんです。
もちろん、試合に負けたときや、思うようにいかないときもある。
でも、そんなときこそ親子でしっかり寄り添って、一緒に“どこに楽しさを見いだせるか”を考えてほしいと思います。
たとえば「○○くん(仲間)、最近頑張ってるよね」なんて親子で会話ができたら、もうそれはすごく素敵なこと。
仲間と一緒に成長を楽しむ。それこそが、団体競技であるサッカーの、本当の醍醐味だと思っています。
どうか、無理のない形で、学校や日常生活も大切にしながら、サッカーを仲間と“楽しむ”場所としてどこのクラブが適しているかという目線でチームを選んでいただければ幸いです。
最後に
インタビューを通して感じたのは、山代代表の姿勢が指導者という枠にとどまらず、教育者としてのまなざしを持っているということでした。
「僕なんてインタビューを受けるような人間じゃないですよ」と笑いながら話してくれたエピソードのひとつに、小学校での“お金の授業(金融教育)”があります。
仕事の一環として挑戦されたそうですが、複数の学校から依頼を受けるほどの反響があり、その姿勢からは、サッカーの枠を超えて子どもたちと向き合う意志が伝わってきました。
クラブで子どもたちと過ごす時間、保護者とのやりとり、地域での教育活動——
どれもが「子どもを育てる」という一本の軸でつながっているように感じます。
社会全体で子どもを支えることが求められている今、こうした存在が地域にいるというのは、とても心強いことだと思います。










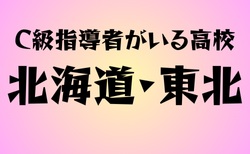

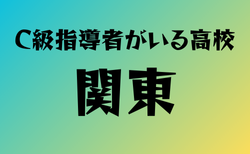



コメント欄