栃木県内で活動するFantasista栃木U-15。
少人数にもかかわらず、フットサルU-15選手権 栃木県大会での優勝・準優勝、さらには関東大会ベスト4入り、全国大会出場と、成果を出し続けています。
その根底にはどんな指導があるのでしょうか?
山崎 亜輝緒監督に、子どもたちを育成する上での想いについてお話を伺いました。
失敗を経験して強くなる
ーーーFantasista栃木 U-15は、フットサルの栃木県大会優勝、2025年1月に行われた全国大会に出場されるなど、華々しい成績を収めながら、女子も含め学年を超えた活動をされていますね。なぜここまで強いチームをつくることができるのでしょうか?
Fantasista栃木 U-15 山崎 亜輝緒監督(以下、山崎)
一番大きいのは“少人数”でやっていることだと思います。人数が限られているからこそ、一人ひとりが自然と責任感を持つようになる。試合でも練習でも、自分がやらなきゃ、っていう意識が強くなるんです。
ーーーそんなに経験豊富な子ばかりではないと伺っています。技術的にはどうやって上達していくのでしょう?
山崎
やっぱり“挑戦の機会”が多いからだと思います。一般的な指導では、『ドリブルするな』『もっとパスをつなげ』など、プレーに制限が多いこともありますよね。でも、うちでは逆にどんどんやらせる。ドリブルでもシュートでも、とにかく自分で判断してプレーさせるんです。その分、成功も失敗もたくさん経験できる。だからこそ、自然と技術も判断力も伸びていくんです。
今年は特に1年生や女の子も多いので、最初は遠慮してしまったり、失敗を恐れてボールから逃げてしまう子もいます。でも、うちでははっきりと言うんです。
『失敗しろ』って(笑)。
ただし、“やらずに後悔する失敗”はダメだよって。
たとえば、『ドリブルしとけばよかった』とか『パス出せばよかった』という“やらなかった”後悔。
挑戦してミスしたなら、それは立派な経験であり、失敗じゃない。
そこから学んでいけばいい。そういう考えを、少しずつ伝えていってます。
ーーー失敗を歓迎するって、勇気のいる指導ですよね。
山崎
サッカーがうまくても、うまくなくても関係ありません。
うちのチームは、とにかく“挑戦したい気持ち”を大事にします。ミスしても、怒られない。むしろ、挑戦しないほうがもったいない。
自分で考えて、自分でプレーして、自分でうまくなっていく。その楽しさを、一緒に味わってもらえたら嬉しいです。
失敗が増えるということは、それだけたくさん“やった”ってことですから。
例えば、難しい場面に2回、3回と挑戦して、失敗が続いても、ある時ふっと1回成功する。すると、子どもたちはその感覚を掴むようになるんです。
でも、そもそも挑戦しなければ、そのタイミングや感覚を一生掴めないまま終わってしまう。
だから、やらせる。
挑戦する経験そのものが宝になると思っています。
ーーー学年も性別もバラバラで、高校生や年上と対戦することもあると聞いています。
山崎
はい、それも当たり前のようにやっています。たとえば、上の学年の試合だから下の子は出さない、というのは普通の考え方だと思います。でも、うちではそういった“線引き”を極力なくしています。学年や年齢を超えて一緒にプレーすることで、自分より上手な相手にも挑戦する。そうやって自然と経験が積み重なっていくんです。
学年ごとにチームを区切ってしまうと、“できる子”が『自分はもうできる』って思い込んでしまう危うさもあると思うんです。自分より強い相手と混ざってやることで、まだまだだと気づくし、逆にチャレンジ精神も養われる。だから、縦のつながりって、すごく大事なんですよ。
ーーーでも、子どもたちの中にはやっぱり失敗を怖がる子もいますよね?
山崎
もちろんです。ほとんどの子は最初、失敗を怖がりますよ。逃げたがる。でも、ちょっとでも前に出られたら、それを“普通に”褒めるようにしてるんです。大げさに褒めるわけではなくて、『それでいいよ』『今のよかったよ』と、ちゃんと認める。そうすると子どもたちも少しずつ変わってくる。今では、僕が言わなくても、チームメイト同士で『行けよ!』『やってみなよ!』って声をかけ合ってくれるようになったんです。
普通だったら、挑戦して失敗したら「何やってるんだ!」って怒られる場面ですよね。
でも、うちは誰も怒らない。
むしろ“挑戦しないこと”のほうが問題で、『なんで行かなかった?行っていいんだよ』って声が飛ぶ。
そうやって、チャレンジが当たり前の空気になっている。それが今のこのチームの強さにつながっているんじゃないかと思います。
ーーー山崎監督の根底にあるのは、子どもたちに挑戦させてあげよう、乗り越えさせてあげよう、経験させてあげようという思いですね。それは、どこから生まれたんですか?
山崎
どうしてでしょうね(笑)
まあ、自分でやらないといけないっていうのが根本にあるのかなと思います。
それと、自分の周りでも、若い頃サッカーが上手だったけど、その後の人生がうまくいかなかったという例を見てきたんです。
だから、子どもたちにはそうなってほしくないというのがあって。
結局、人生って自分でなんとかしないといけない場面が必ずくるんですよ。
親もずっとはそばにいてあげられない。だからこそ、自分の力で乗り越える経験を今のうちにしてほしいんです。
でも、経験だけでよいのか、勝負にこだわらなくてよいのか、といわれるとちょっと違う。
僕自身もサッカー経験の中で県大会優勝や、全国大会優勝などを味わってきました。
だから、勝負に対してはすごくこだわっています。
試合のモチベーションの持っていき方とか、時間の使い方とか、そういう部分には結構細かく気を遣っていますね。
ただ、それを一方的に指示するのではなくて、“こういう時はこうした方がいいよ”と伝えるようにしています。
勝負どころでは、きっちり勝負する。そこは子どもたちにも伝えています。
伸ばすチャンスをつくる
ーーー山崎監督は学習塾の塾長でもあります。 勉強も見て、サッカーも見てという関わり方の中で、子どもたちとの3年間ってものすごく濃い時間になっているのではないでしょうか?
山崎
そうですね。今はもうそれが自分の生きがいになってます。もともとは学習塾だけをやってたんですけど、塾って合格したら『はい、さようなら』で終わってしまう。でもサッカーを一緒にやるようになってからは、卒業後の進路も見えるし、成長もより深く見届けられるようになったんです。
サッカーの時と勉強している時、遊んでいる時、それぞれの顔がまったく違うんですよ。サッカーでは勝てないけど、勉強なら強い、逆にサッカーのパスは得意だけど勉強は苦手とか。そうやって“絶対的な序列”をつくらないようにしています。そうすると自然とそれぞれの得意を認め合う空気ができるし、評価の仕方もひとつじゃなくなる。それがすごく面白いですね。
レギュラーの子が絶対って空気にもならない。勉強ではこっちの子を頼ってみようって場面がつくれる。そういうバランスがあるから、みんなの可能性が広がっていくように感じています。
勉強を見てる時に、“あ、ちょっと成長したな”って感じる瞬間って、結構あるんですよ。
たとえば、最初は何を言っても『うん』しか返ってこなかった子が、『はい』って一言返せるようになる。そんな小さな変化ですけど、それがサッカーでも表れてきたりするんですよね。
ーーーそういう変化に気づいた時、子どもにどんな風に伝えるのですか?
山崎
直接は言わないです。
その代わり、サッカーの練習の中で、その子の変化がより活きるように工夫します。うちは、ミニゲームやパスゲームのチーム分けも全部僕が組んでるんですよ。「選手が勝手に組み分けする」は一切ない。
たとえば、いつもリーダーシップをとってる子をあえて別チームに置いて、そのポジションに成長してきた子を入れてみる。すると、その子が初めて声を出すきっかけになるかもしれない。そういうチャンスを随所で与えたいんです。
そんなふうに、成長のタイミングを見て、伸ばすチャンスをつくってあげるようにしています。
褒めるよりも、次の経験にどうつなげてあげるか。それが一番大事かなと思っています。
学年を超えた活動
挑戦を応援する心が育つ
ーーーファンタジスタの子どもたちを自慢してください!
山崎
やっぱり“挑戦することに対する応援”が自然とできるようになってきてる、ってところは自慢できると思いますね。
今、U-15リーグっていう大会に出ているんですけど、うちは3年生が中心のリーグに、1年生から出場させてるんですよ。
で、1年生がボール持ってドリブルで仕掛けようとすると、普通だったら上級生が『出せ!』って言いがちじゃないですか。でもうちの3年生は『行け!』『行け行け行け、自分でいけ!』って声をかけるんです。すごいなと思いますね。
取られても『自分で取り返せ!』って言うんですよ。見てて、ほんとに感心します。もちろん、自分たちもプレーしますけど、“ここはこの子が行くべきだ”って思ったらちゃんと任せるんです。任せたうえで、責任も背負わせる。これ、最近の試合でもあって、ビデオにも残ってると思います。
最近、そういう場面が見えるようになってきましたね。僕も素晴らしいなと思ってます。
普段から1年生から3年生まで一緒に練習してるので、そういう関係性ができているのかもしれません。
(U-15のリーグの一幕。3年生が1年生に並走しながら、「行け!」と励まし続けているの、聞こえますか?)
ーーー学年をミックスして練習しているのですね。
山崎
そうです。学年関係なく一緒にやってます。だから例えば、サッカー経験がまったくない子が入ってきても、自然とその中で育っていくんですよ。
この前も、急に埼玉から引っ越してきた子がいて、中学にサッカー部がないことが分かったって、4月頭くらいに連絡が来たんです。まったくの初心者。でも今、ちゃんとやってますよ。
その子、けっこうおしゃべりもできる子だったんで、先輩たちもちゃんと話を聞くし、同級生も関わってくれるし、みんなで自然と受け入れてますね。そういう空気がうちにはあると思います。
ーーー初心者で入ってきた子も、すぐにチームに溶け込めるんですね。
山崎
そうですね。その子、たしか野球経験があったんです。で、ある時ミニゲームの時に『おい、ちょっとキーパーできんじゃね?』って冗談交じりに言ったら、意外とできて。そしたら3年生たちが『すごいじゃん!』って褒めてくれて、最近はキーパーとしても頑張ってますよ。
うちではキーパー“だけ”って子はいないんです。基本的にはフィールドもキーパーも両方やらせてます。今どきのキーパーは足元の技術も必要ですしね。
だから、例えば公式戦ではキーパーをやったら、そのあとのフレンドリーマッチではフィールドをやらせる。そういう風にしてます。
ディフェンスだけとか、フォワードだけっていう固定の起用はなるべく避けてます。
もちろん、リーダー的な子がいたらそっちに任せることもありますけど、基本は僕が決めてます。『最近この子、ここやってないな』と思ったら、意図的に別のポジションをやらせてみたり。
ただ、ゲームが壊れないようには調整してますよ。例えば主力の子はここに置いておこうとか、あとは……まあ、自分も出てます(笑)
ーーー山崎監督も現役選手ですもんね。
山崎
はい。自分も楽しみにしてます(笑)。
現役といえば現役なんですけど、なかなか時間もなくて。
プロフィールで見たっていうマスターズリーグ、あれも出られてないんですよ。
まあ、中学生と一緒にやるくらいがちょうどいいですね。
今は1年生が多いので、上級生とやると格の違いで押されちゃうこともあって。
僕がチームに入って、バランスを取ってます。
ーーー最後に小学生とその保護者に向けてのメッセージをお願いします。
山崎
栃木県では、技術的なことをじっくり取り組むスタイルのチームって、実はあまり多くはないんです。
だからこそ、技術にこだわりたい子や、自分でやりたいことに挑戦したい子には、ぜひ来てほしいと思っています。
それに、最初から『うちの子には無理じゃないか』なんて決めつけないでほしいんです。親御さんの目から見て難しそうに見えることでも、実際にやってみたらすごく伸びる、なんてことも本当にたくさんあります。
うちは初心者の子も大歓迎ですし、経験や今の力で可能性を狭める必要はまったくありません。
体験に来て、雰囲気を見て、自分の目で感じてもらえると嬉しいです。
10代前半なんて、まだまだこれからです。可能性はいくらでもありますよ。
最後に
「失敗しろ」と言い切る指導者は、そう多くはありません。
しかし山崎監督の言葉からは、その失敗を経験と捉え、次に活かす文化を築いていることがよく伝わってきました。
学年や経験を超えて活動を共にすることも印象的です。
挑戦すること、成長のタイミングを逃さずに“伸ばすチャンス”を与えること。子どもたちの可能性を信じる大人がいる場所は、本当に力強いと感じました。
これからもFantasista栃木U-15が、挑戦を応援できる心を育む場であってほしいと思います。









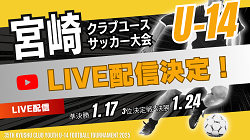
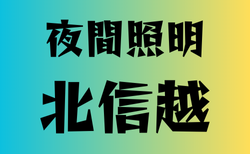
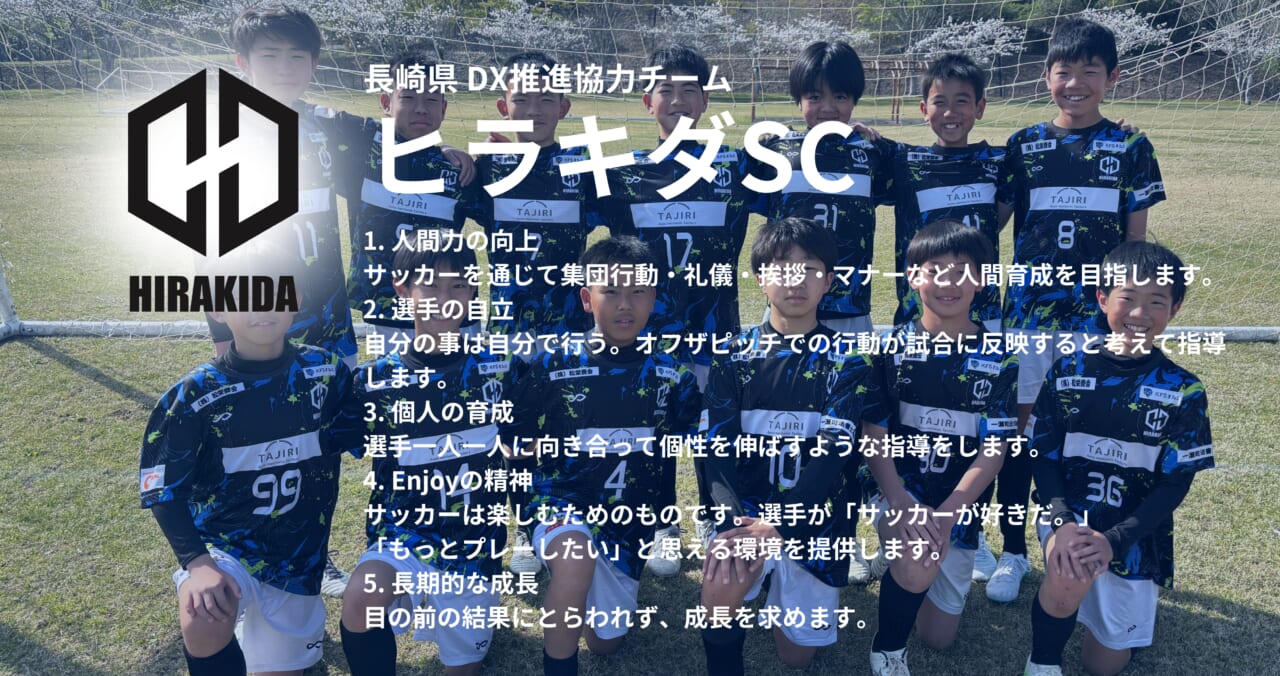

コメント欄